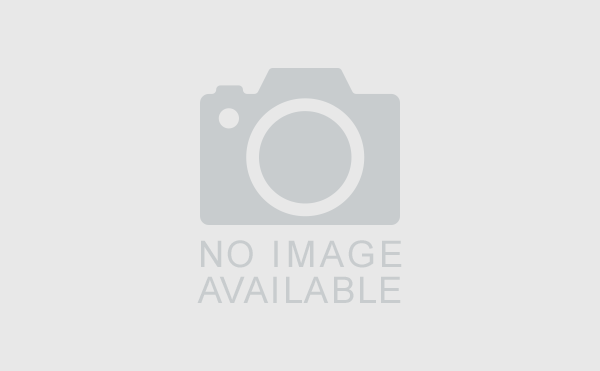ネットでのトラブルと法律について
SNSやブログ、掲示板など、インターネット上でのやり取りは今や日常の一部となっています。しかし、発信が簡単になった一方で、誹謗中傷や無断転載、情報漏洩などのトラブルも増加しています。本コラムでは、ネット上の代表的なトラブルと、それに関係する法律、そしてフリーランスや企業が取るべき対策について解説します。
- ネット上のトラブルとは?
ネットトラブルとは、インターネット上でのやりとりに起因する法的・社会的問題を指します。匿名性や拡散力の高さから、小さな投稿が大きな問題に発展することも珍しくありません。具体的には以下のようなものがあります。
- SNSや掲示板での誹謗中傷
- 他人の著作物(画像・文章など)の無断使用
- 個人情報の漏洩・悪用
- 虚偽の情報による風評被害
- よくあるネットトラブルの法律関係
ネットトラブルには、以下のような法律が関係してきます。
| トラブル内容 | 関連する主な法律 |
| 誹謗中傷 | 名誉毀損(刑法230条)、侮辱罪(刑法231条)、不法行為(民法709条) |
| 無断転載 | 著作権法(第21条:複製権、第23条:公衆送信権など) |
| 個人情報の漏洩 | 個人情報保護法、民法(709条:不法行為) |
| 虚偽情報の拡散 | 不正競争防止法(誤認表示等)、名誉毀損、信用毀損 |
加害者が特定できない場合でも、プロバイダ責任制限法(発信者情報開示請求)によって投稿者を特定する手段もあります。
- ビジネスにおける注意点
インターネット上の発信は、フリーランスであっても企業であっても「業務の一環」と見なされるケースが少なくありません。トラブルを未然に防ぐために、様々なことに注意をしなくてはいけません。一例をとして下記が挙げられます。
- 無断で画像や音源を使用しない(特に商用利用時は著作権に要注意)
- SNSやブログなどでの不用意な発言を避ける(他人やクライアントの評判を下げる表現など)
- 顧客対応時やトラブル発生時の言動が炎上につながる可能性を意識する
- 担当者やチームメンバーへの情報モラル・SNSリスクに関する指導を行う
- 発信が「会社の公式見解」と誤解されるリスクを理解し、個人と業務の線引きを明確にする
- 実務でよくあるネットトラブル事例
ネット上での発言や投稿が、損害賠償責任に繋がった事例も存在します。
以下はその一部です。
- 従業員のSNS投稿による企業イメージ毀損
- ある企業の従業員が、自社や上司に対する誹謗中傷を個人SNSで投稿。企業の社会的評価が低下し、裁判所は就業規則違反および名誉毀損に基づき、従業員に損害賠償の支払いを命じた。
- フリーランスによるクライアント批判と契約解除
- フリーランスが業務中にクライアント対応への不満をSNSで発信し、企業イメージを損なったことから契約解除と損害賠償請求へ。裁判所は守秘義務違反と名誉毀損にあたると判断。
- 企業公式SNSアカウントの不適切投稿による訴訟
- 企業のSNS担当者が競合他社を揶揄する投稿を行い、名誉毀損として訴訟に。企業の公式アカウントであることから、会社に対して損害賠償責任が認定された。
これらの事例は、業務の一環として行われるネット発信が重大な法的責任を生む可能性を示しています。
こうした事例が示すように、インターネット上の発信も現実の法的責任を伴うものであり、「ネットだから問題にならない」という油断は大きなリスクにつながります。
- 実務でできる予防策
ネットトラブルを防ぐために、以下のような対策が有効です:
- ガイドラインの策定:投稿・発言のルールを社内で共有
- 著作権・個人情報に関する研修:法律の基本をチームで学ぶ
- 炎上対策マニュアルの整備:トラブル発生時の対応フローを明確に
- 契約書での責任分担の明確化:業務委託契約にSNSリスクの責任範囲を明記
- まとめ
ネットの利便性と引き換えに、法的リスクも増加しています。些細な発言や投稿が、法的責任や損害賠償請求に発展することもあります。フリーランスも企業も、自分や自社の発信がどのような影響を持つかを理解し、リスクを最小限に抑える工夫が求められます。
日々の発信において「これって大丈夫かな?」と思ったときこそ、一歩立ち止まって確認する習慣が、将来のトラブルを防ぐ第一歩です。