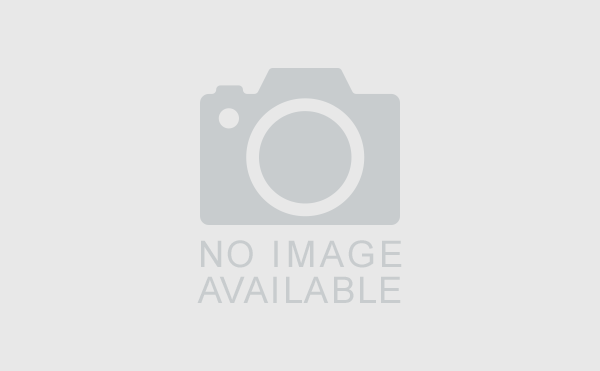時効とは?ビジネスで知っておきたい基本と注意点
ビジネスにおいて取引や契約を行う際、「時効」という制度は見逃せないリスク管理のひとつです。請求できる権利があるのに、気づいたときには時効で消えていた――そんな事態を防ぐために、時効の基本と実務上の注意点を分かりやすく解説します。
- 時効とは?(民法166条ほか)
時効とは、一定の期間が経過することで、ある法律上の効果が発生する制度です。
民法では、大きく分けて次の2種類があります。
- 消滅時効:一定期間が経過すると、権利(例:代金請求権)が消滅する
- 取得時効:一定期間占有し続けることで、所有権などを取得できる
本コラムでは、特にビジネスで関係の深い「消滅時効」に焦点を当てます。
- 時効期間の基本
2020年4月の民法改正により、消滅時効のルールが整理され、以下のようになりました。
- 権利を行使できると知った時から5年
- 権利を行使できる時から10年(知ったかどうかに関係なく)
この2つの期間のいずれか早い方が時効完成の基準になります。ただし、債権者自身がその権利の存在に気づくことが難しいような特別なケース(例:過払い金返還請求など)では、「権利を行使できるときから10年」のルールが適用されることもあります。
例:請負契約の場合
納品完了から報酬未払いが続き、5年が経過した場合、請求権が消滅する可能性があります。
- 時効が使われる場面と注意点
ビジネスでは以下のような場面で時効が問題になります。
- 報酬未払いの請求:過去の業務委託報酬を請求しようとしたが、時効にかかっていた
- 損害賠償請求:トラブル発生から長期間経過していたため、請求が通らなかった
- 借金・貸付金の返還請求:最後の返済から一定期間が過ぎていた
時効完成を防ぐには、催告(請求)や訴訟の提起によって時効を中断させることが有効です。
- フリーランス・企業が気をつけたいポイント
時効制度は、フリーランスや企業にとって大きな影響を与えます。その為以下のような対策が重要です。
- 契約書に時効に関する条項を盛り込む:民法上の時効期間を延長・短縮することも可能です(ただし制限あり)
- 請求は速やかに行う:請求書を放置せず、やり取りの記録も残しておく
- 定期的な債権管理を行う:回収漏れや請求忘れを防ぐ体制づくりが重要
- 内容証明郵便や訴訟で時効の中断を図る:書面での正式な請求は、時効中断の効果があります
- 時効の中断と更新(民法147条〜)
時効は、一定の行為によって「中断」または「更新」されることがあります。
- 中断:訴訟提起、支払督促、差押えなど
- 更新:裁判で確定判決を得た場合、そこから再度時効がスタートします
一度中断したからといって安心せず、「いつから再カウントになるのか」も管理する必要があります。
- まとめ
時効は、請求できる権利を「使わなかったことで消えてしまう」リスクです。ビジネスの現場では、債権の管理や契約内容の確認を通じて、時効にかからないように注意を払うことが求められます。
特にフリーランスや企業の法務担当者にとっては、請求のタイミングや証拠の保全など、日々の対応が時効対策の鍵となります。万が一のトラブルに備え、しっかりと準備をしておきましょう。