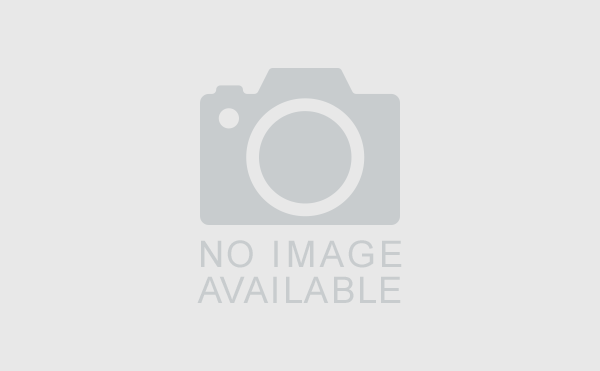示談とは?
トラブルが発生したとき、「裁判ではなく示談で解決する」といった表現を耳にしたことがある方も多いでしょう。示談はビジネスの現場でも活用される紛争解決手段の一つです。本コラムでは、示談の意味や特徴、契約実務での注意点について、わかりやすく解説します。
- 示談とは?(民法695条)
示談とは、当事者間で話し合いにより争いごとを解決する合意のことです。法的には「和解契約」と呼ばれ、民法695条に定義されています。
| (和解) 第695条 和解は、当事者が互いに譲歩してその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。 |
裁判をせずに解決を図るという点で、コスト・時間の削減、関係維持といったメリットがあります。
1-1. 示談に関係するその他の法的根拠
示談は民法695条に基づく「和解契約」ですが、実務では他にもさまざまな法的原則や条文が関係してきます。以下に代表的なものをまとめます。
| 項目 | 解説 |
| 契約自由の原則(民法521条など) | 示談も契約の一種なので、当事者間の自由な合意によって成立します。 |
| 強制執行力の担保(民事執行法22条など) | 示談書を公正証書にしておけば、未払い時に強制執行が可能です。 |
| 名誉・プライバシー保護(民法1条2項など) | 示談の内容によっては、信義則や人格権との関係も検討が必要です。 |
| 刑事事件との関係 | 民事的に示談が成立しても、刑事責任がなくなるわけではありません(ただし量刑に影響する場合があります)。 |
- 示談と和解契約の違いは?
実務上、「示談」と「和解契約」はほぼ同義に扱われます。ただし、
-
- 「示談」:日常用語として広く使われる
- 「和解契約」:法律用語としての正式な表現
という違いがあります。ビジネス文書や契約書では「和解契約書」などの表現が一般的です。
- 示談のメリットとデメリット
メリット:
-
- 裁判よりも早期解決が可能
- 費用が少なく、柔軟な条件での解決が可能
- 関係性の維持が期待できる
デメリット:
-
- 相手方の合意が得られないと成立しない
- 権利を一部放棄することになるケースも
- 強制力が裁判に比べて弱い(ただし公正証書化などで担保可)
- 示談書を作成する際の注意点と判例から見る注意点
示談を成立させる場合は、**示談書(和解契約書)**を作成することが極めて重要です。以下の点を明確に記載しましょう。
-
- 紛争の内容と事実関係の確認
- 解決金・支払い条件
- 今後の責任追及を行わない旨(清算条項)
- 守秘義務、名誉毀損回避など
また、署名・押印を確実に行い、2通作成して当事者双方が1通ずつ保管するのが原則です。
実務上の判例から見る注意点
-
- 将来の損害が予見できない場合:示談時に予期できなかった後遺障害が発生した事例では、最高裁が追加の損害賠償請求を認めた(昭和43年3月15日判決)。示談書に「将来の損害にも及ぶ」と書かれていなければ、追加請求の余地がある。
- 示談金額が社会通念上不相当な場合:過度に高額な示談金は、公序良俗違反として無効とされる可能性がある(東京地裁 平成28年12月15日判決)。双方の交渉力に大きな差がある場合は特に注意。
- 再請求条項の有無が重要:後から損害が発生した場合に備え、「将来請求を妨げない」旨の条項を設けることで、後の追加請求がしやすくなる(名古屋地裁 平成30年2月20日判決)。
- ビジネスにおける示談の活用場面
フリーランスや企業の現場でも、示談は以下のようなトラブル解決に使われます。
- 業務委託契約の解除時の条件整理
- 報酬未払い・成果物の瑕疵に関する協議
- ハラスメント・誹謗中傷に関する和解
- 損害賠償請求に関する話し合い
「大ごとにはしたくないが、きちんと解決しておきたい」ときに、示談は非常に有効な手段となります。
- 示談と秘密保持
示談においては、「外部に内容を漏らさない」ことが条件となることが多く、秘密保持条項を設けるのが一般的です。特にハラスメントや名誉毀損に関する示談では、SNS等での拡散リスクを防ぐためにも重要なポイントとなります。
- まとめ
示談は、当事者間の話し合いで柔軟かつスピーディにトラブルを解決する手段です。裁判よりも負担が軽く、ビジネス現場でも広く活用されています。
ただし、示談はあくまで「合意」が前提となるため、交渉力や文書化のスキルも問われます。トラブル発生時には、感情的にならず、冷静に条件を整理し、示談書に残すことで安心できる解決を図りましょう。